西の湖美術館づくり その4 あるべき姿
2013年08月16日
連続の「西の湖美術館づくり」報告です。
目標とした西の湖のラムサール条約の追加登録も3年前に実現し、昨年度の近江八幡市との合併のよる新たな動きもでてきています。
「東近江水環境自治協議会」の多岐にわたる構想と提案、更には具体的成果を引き継ぎながら、私たちも次の行動に着手していきます。
美術館づくりのあるべき姿(視点と目標)
美術館づくりのあるべき姿をイメージだけに頼ることは充分ではありません。干拓前の内湖群の景観を知っている人にとっては有効であっても、これらコトバを頼りに引き出されるイメージはその人の年代や経験の差によって同一とはかぎりません。
そこで、より明確な視点と目標が必要となります。その内容は次の通りです。

景観保全への視点と目標
A.古きを訪ねることから始める
縄文の昔からつい数十年前まで、この内湖群の水環境と景観は、おそらく2,000年以上、大きく姿を変えてこなかったものと推定されます。
我々の先祖は日々の暮らしのなかで、水をいのちの水としてその汚れに日々注意を払って大切に守ってきました。また自然の恵みに感謝しつつ漁をおこない、ヨシ原の手入や湖底のモラ採り(湖底の藻や水草を泥土とともに採取すること。肥料に使う)を行なうなど持続可能な日々の営みの継続によって、豊かで美しい景観を我々の世代に引継いでくれたと考えてよいでしょう。
それからたった数十年、営々と引継いできた先祖の努力を大きく変える事柄が立て続けに起こってきました。
この地域の環境と景観を大きく変化させてきたものは、小中の湖・大中の湖の干拓と舟運が自動車運送に取って代わられたことによる港や水路の消滅と道路の建設、そして水辺保全の関心を失わせた上水道の普及です。
利便性を追い求めた結果、失われてしまった景観が果たしていた役割は何であったかを見つけ出し、今に生かす工夫が求められます。
B.この地の歴史遺産はそれを取り巻く水の景観と共にわが国にとって大切な遺産
大中の湖、小中の湖、西の湖の内湖群は中世に長くこの地を治めた佐々木氏、近世の扉を開けた織田信長や豊臣秀次が、わが国の歴史に残る城の築城と城下町の形成、楽市楽座の創設に当たって、舟運と言う当時の人及び物の流れを支える大動脈を考慮した上で立地した要衝の湖でありました。
この地が我が国にとって歴史的にも、文化的にもいかに重要なスポットであるかはNHKの大河ドラマに頻繁に登場することをみても明らかです。
世界の主な都や都市は川や湖などの水辺にあります。そして、その水域と調和した建造物や町並みが美くしい景観を形成し、長く保全されていることを考えた時、たとえ短期間であったにせよ日本の都であり、世界にもその壮大さと美しさが伝えられた安土城の立地理由となった内湖群を、保全の対象から除外して我々の世代が簡単に消滅させてしまったことに今となっては強い疑問を抱きます。
世界では世界遺産が文化遺産、自然遺産、そしてその両者によって作り出される複合遺産と言う分類によって保護されています。時変り、わが国も景観法の制定によってやっとその保護に乗り出していることの重要さを意識すべきであるし、それが私達の暮らしの質の向上につながると考えるべきでしょう。
C.持続可能な社会への入り口は景観と保全と生活文化づくりから
環境団体である当会がなぜ「西の湖美術館づくり」を言い出したのかは次の気づきがあったからです。
西の湖周辺のヨシ原に代表される自然の風景は、手つかずの自然ではありません。どこかで必ず人の手がは入った自然になっています。風景はその時代の暮らしを映し出している鏡なのです。暮らしが荒れたらヨシ原も荒れる。町並みの乱れはコミュニテイの乱れ、風景(景観)の荒れようや乱れようを見て自分達の生活を省みる。
持続可能な社会へのアプローチは風景(景観)の保全から入るのが案外早道かもしれないと考えるようになったからです。
また、かってこの地には多くの人が農作業や漁業の傍ら謡曲や、和歌、俳句を嗜み、連歌の会を小中の湖の弁天島で楽しむなどの伝統がありました。
このような伝統を踏まえて新しい生活の楽しみを作り出そうとヨシに因んだイベント(ヨシ舟による沖島渡り)、祭り(ヨシ松明祭り)コンサート(ヨシ笛コンサート)、絵画(ヨシペン画)、物語(ヨシ物語の紙芝居)、狂言(琵琶の湖、琵琶の湖その後)などに取り組んできましたので、これを美術館づくりの中で取り上げて地域の人に流行らせたいとおもっています。
持続可能な社会は沈滞した社会ではありません。明治維新以来の富国強兵の陰に押しやられて低い評価を受けていた江戸時代が、物については持続可能な社会を形成する傍ら、花見、園芸、花火、浮世絵、芝居、浮世風呂など世界的に見ても質の高い生活を楽しむ庶民文化を花開かせていた時代だったことを思い出すなら、このような生活文化の推奨もまた持続可能な社会への入り口となると思っています。

D.目標
a.現存する水郷については、すでに近江八幡市が「水郷風景計画」として住民意見を求めておられる段階にあります。当会としては安土町が早急にこの計画と調和の取れた計画の推進を求めます。
b.それとともに消失した湿地の再生が世界的な課題となっていることからも内湖の復元に取り組む必要があります。しかしながら現状はそこで働き、そこに住む人がいる限り容易な問題ではありません。そこに住む人達のご意向と、湿地再生の動向を見ながら、次のステップで対応したいと考えます。
1)景観法に基づく保全を小中の湖の干拓地、大中の湖の干拓地の農地にまでおよぼすこと、ラムサール条約の対象にこの地域を加えることなどの現状保全を進めることが先ずその第一歩です。
2)次いで、干拓前の地図は有りますし、残された写真は少ないものの干拓前の景観を記憶している人も残っていますので、この人たちの記憶を記録に止める活動を行なうことにより(現在進行中)、これ等を参考に現状で可能な復元をおこなうことが次のステップとなります。
3)また、高齢化の進行や少子化により跡継ぎが無く放置される田畑が生じた時などの機会を捉えて更に復元を進めることが景観保全の目標になります。
目標とした西の湖のラムサール条約の追加登録も3年前に実現し、昨年度の近江八幡市との合併のよる新たな動きもでてきています。
「東近江水環境自治協議会」の多岐にわたる構想と提案、更には具体的成果を引き継ぎながら、私たちも次の行動に着手していきます。
美術館づくりのあるべき姿(視点と目標)
美術館づくりのあるべき姿をイメージだけに頼ることは充分ではありません。干拓前の内湖群の景観を知っている人にとっては有効であっても、これらコトバを頼りに引き出されるイメージはその人の年代や経験の差によって同一とはかぎりません。
そこで、より明確な視点と目標が必要となります。その内容は次の通りです。

景観保全への視点と目標
A.古きを訪ねることから始める
縄文の昔からつい数十年前まで、この内湖群の水環境と景観は、おそらく2,000年以上、大きく姿を変えてこなかったものと推定されます。
我々の先祖は日々の暮らしのなかで、水をいのちの水としてその汚れに日々注意を払って大切に守ってきました。また自然の恵みに感謝しつつ漁をおこない、ヨシ原の手入や湖底のモラ採り(湖底の藻や水草を泥土とともに採取すること。肥料に使う)を行なうなど持続可能な日々の営みの継続によって、豊かで美しい景観を我々の世代に引継いでくれたと考えてよいでしょう。
それからたった数十年、営々と引継いできた先祖の努力を大きく変える事柄が立て続けに起こってきました。
この地域の環境と景観を大きく変化させてきたものは、小中の湖・大中の湖の干拓と舟運が自動車運送に取って代わられたことによる港や水路の消滅と道路の建設、そして水辺保全の関心を失わせた上水道の普及です。
利便性を追い求めた結果、失われてしまった景観が果たしていた役割は何であったかを見つけ出し、今に生かす工夫が求められます。
B.この地の歴史遺産はそれを取り巻く水の景観と共にわが国にとって大切な遺産
大中の湖、小中の湖、西の湖の内湖群は中世に長くこの地を治めた佐々木氏、近世の扉を開けた織田信長や豊臣秀次が、わが国の歴史に残る城の築城と城下町の形成、楽市楽座の創設に当たって、舟運と言う当時の人及び物の流れを支える大動脈を考慮した上で立地した要衝の湖でありました。
この地が我が国にとって歴史的にも、文化的にもいかに重要なスポットであるかはNHKの大河ドラマに頻繁に登場することをみても明らかです。
世界の主な都や都市は川や湖などの水辺にあります。そして、その水域と調和した建造物や町並みが美くしい景観を形成し、長く保全されていることを考えた時、たとえ短期間であったにせよ日本の都であり、世界にもその壮大さと美しさが伝えられた安土城の立地理由となった内湖群を、保全の対象から除外して我々の世代が簡単に消滅させてしまったことに今となっては強い疑問を抱きます。
世界では世界遺産が文化遺産、自然遺産、そしてその両者によって作り出される複合遺産と言う分類によって保護されています。時変り、わが国も景観法の制定によってやっとその保護に乗り出していることの重要さを意識すべきであるし、それが私達の暮らしの質の向上につながると考えるべきでしょう。
C.持続可能な社会への入り口は景観と保全と生活文化づくりから
環境団体である当会がなぜ「西の湖美術館づくり」を言い出したのかは次の気づきがあったからです。
西の湖周辺のヨシ原に代表される自然の風景は、手つかずの自然ではありません。どこかで必ず人の手がは入った自然になっています。風景はその時代の暮らしを映し出している鏡なのです。暮らしが荒れたらヨシ原も荒れる。町並みの乱れはコミュニテイの乱れ、風景(景観)の荒れようや乱れようを見て自分達の生活を省みる。
持続可能な社会へのアプローチは風景(景観)の保全から入るのが案外早道かもしれないと考えるようになったからです。
また、かってこの地には多くの人が農作業や漁業の傍ら謡曲や、和歌、俳句を嗜み、連歌の会を小中の湖の弁天島で楽しむなどの伝統がありました。
このような伝統を踏まえて新しい生活の楽しみを作り出そうとヨシに因んだイベント(ヨシ舟による沖島渡り)、祭り(ヨシ松明祭り)コンサート(ヨシ笛コンサート)、絵画(ヨシペン画)、物語(ヨシ物語の紙芝居)、狂言(琵琶の湖、琵琶の湖その後)などに取り組んできましたので、これを美術館づくりの中で取り上げて地域の人に流行らせたいとおもっています。
持続可能な社会は沈滞した社会ではありません。明治維新以来の富国強兵の陰に押しやられて低い評価を受けていた江戸時代が、物については持続可能な社会を形成する傍ら、花見、園芸、花火、浮世絵、芝居、浮世風呂など世界的に見ても質の高い生活を楽しむ庶民文化を花開かせていた時代だったことを思い出すなら、このような生活文化の推奨もまた持続可能な社会への入り口となると思っています。

D.目標
a.現存する水郷については、すでに近江八幡市が「水郷風景計画」として住民意見を求めておられる段階にあります。当会としては安土町が早急にこの計画と調和の取れた計画の推進を求めます。
b.それとともに消失した湿地の再生が世界的な課題となっていることからも内湖の復元に取り組む必要があります。しかしながら現状はそこで働き、そこに住む人がいる限り容易な問題ではありません。そこに住む人達のご意向と、湿地再生の動向を見ながら、次のステップで対応したいと考えます。
1)景観法に基づく保全を小中の湖の干拓地、大中の湖の干拓地の農地にまでおよぼすこと、ラムサール条約の対象にこの地域を加えることなどの現状保全を進めることが先ずその第一歩です。
2)次いで、干拓前の地図は有りますし、残された写真は少ないものの干拓前の景観を記憶している人も残っていますので、この人たちの記憶を記録に止める活動を行なうことにより(現在進行中)、これ等を参考に現状で可能な復元をおこなうことが次のステップとなります。
3)また、高齢化の進行や少子化により跡継ぎが無く放置される田畑が生じた時などの機会を捉えて更に復元を進めることが景観保全の目標になります。
Posted by
西の湖観光
at
23:25
│Comments(
0
) │
西の湖美術館




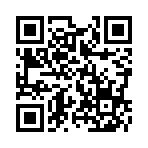


書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。